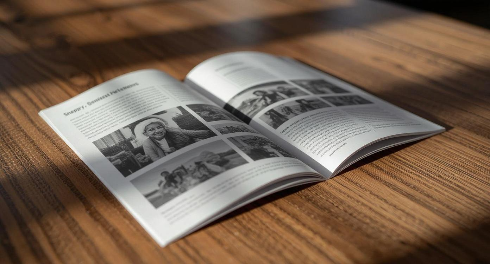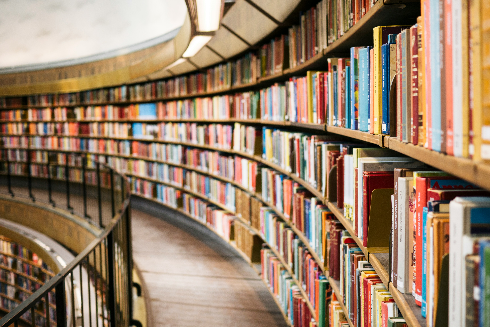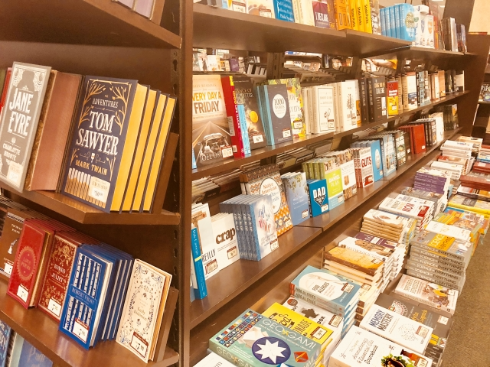中綴じに向く紙・向かない紙|紙厚・仕上がり・用途別の正しい選び方

冊子制作で見落とされがちなのが、用紙選択の重要性です。同じデザイン、同じページ数でも、用紙が変われば仕上がりの印象も使い心地も大きく変わります。特に中綴じは、針金で中央を留めるという構造上、用紙の厚みや質感が製本の成否を左右します。
薄すぎる紙は裏移りが発生し、厚すぎる紙は針金の強度が不足します。中綴じならではの「平らに開く」という特性も、用紙によって変わってきます。どのような紙が中綴じに適しているのか、逆に避けるべき紙は何か。今回は紙厚、仕上がり、用途という3つの視点から、中綿じに最適な用紙選択の基準を解説します。
続きを読む>>