中綴じ冊子って何ページまで?製本の仕組みと注意点
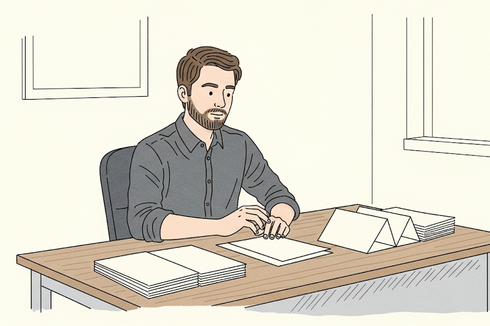
「中綴じって何ページまで綴じられるの?」「印刷してから綴じるの? 折ってから?」といった疑問をお持ちの方は意外と多いかもしれません。見た目がシンプルで仕上がりも軽やかな中綴じ製本ですが、製本のしくみには少しだけ理解が必要です。ページ数の制限やデータ作成時の注意点も含め、知っておくと安心なポイントをご紹介します。
・中綴じの製本構造と仕組み
中綴じとは、印刷した紙を重ねて中央で二つ折りにし、真ん中をホチキスのような針金で綴じる製本方式です。学校のパンフレットや会報誌、小冊子などでよく見かける形式で、シンプルでコストを抑えられることから広く使われています。製本の都合上、ページ数は「4の倍数」で構成されます。これは、1枚の紙に4ページ分(表裏・左右)が割り当てられるためで、たとえば8ページ・12ページ・16ページ…といった区切りで構成する必要があります。
ページ数の上限は「紙の厚さ」によって変わる
中綴じにはページ数の上限があります。これは綴じる紙を中央で重ねて折る構造上、あまりに分厚くなると綴じきれなくなったり、仕上がりにズレが出たりするからです。弊社『冊子印刷ドットコム』では、中綴じ冊子は表紙込みで最大40ページまでに対応しています。薄手の紙を選べば比較的多くのページ数でも対応可能ですが、読みやすさや折り具合とのバランスを考えると、32〜36ページ程度までに抑えるのが実用的というケースも多いです。中綴じならではの注意点とは
中綴じ冊子では、綴じたときにページの中央が内側に引き込まれる「ノド側の巻き込み」や、ページがずれる「小口側のズレ」が発生しやすくなります。特にページ数が多い場合や紙が厚い場合には、端のページほど外側に押し出される形となり、仕上がりが波打ったようになることもあります。また、写真や文字が中央に寄りすぎていると、折り目にかかって読みにくくなる場合もあるため、レイアウト設計では中央付近の余白を少し広めに取ることをおすすめします。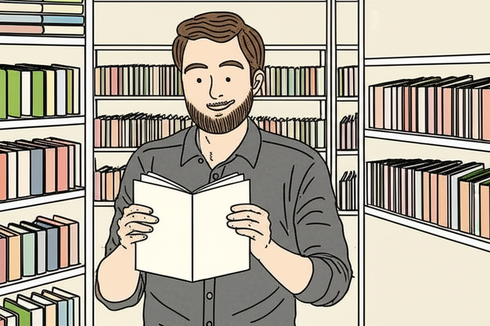
冊子印刷ドットコムなら安心のサポート体制
中綴じ冊子を初めて作る方でも、『冊子印刷ドットコム』なら安心です。ページ数や紙の厚さに応じたアドバイスが受けられ、製本不備のないデータ作成のコツも丁寧にフォローします。ご入稿はPDF形式が基本ですが、専用の入稿チェック機能を使えば、自動でレイアウトやページ数の確認も可能。中綴じ対応の見積りや納期の目安もすぐに確認できます。納期が急ぎの方にも対応しており、小ロット(10部〜)のご注文にも対応しています。薄くて軽く、めくりやすい中綴じ冊子は、学校行事や社内報、フリーペーパーなどさまざまな場面で活躍します。ページ数の上限を把握し、レイアウトに注意して作れば、見やすく美しい冊子が仕上がります。印刷や製本のことがよくわからないという方も、ぜひ一度ご相談ください。



















