企業で活用したいハンドブックの魅力
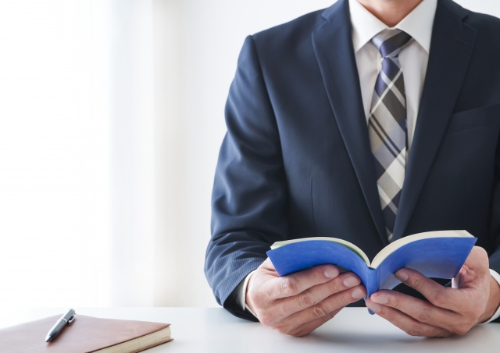
手元に携帯して、必要な時にすぐに参照できる小型の冊子、いわゆる「ハンドブック」は、デジタルツールでは代替できない独自の価値を持っています。
今回は、企業や組織におけるハンドブックの重要性と、効果的な活用方法についてご紹介します。
ハンドブックは、文字通り「手元に置く本」という意味を持ちますが、特定の分野や業務に関する重要な情報をコンパクトにまとめた、携帯可能な冊子のことを指しています。
主にA5サイズ以下で印刷され、手引き書や案内書、便覧、入門書などに広く用いられています。 ハンドブックの主な特徴としてまず挙げられるものが、その携帯性の高さでしょう。
必要な時にすぐに取り出せるサイズで、持ち運びが容易なページ数で印刷されます。
A5サイズやB6サイズなど、服のポケットやカバンに収まるサイズが一般的です。
また即時性の高さもメリットとなります。多くのデジタルツールと違い、電源や通信環境に依存せず、必要な情報にすぐにアクセスできることから、災害時や緊急時での活用法があらためて注目されています。
画面を拡大・縮小する手間を省き、情報を見開きで一覧できるため、情報の把握や比較・検討も容易になります。
ハンドブックが果たす役割
では、企業の業務活動の中でハンドブックが果たす役割には、どのようなものがあるでしょうか?
1)情報の標準化
組織内での情報や手順の標準化は、業務の属人化を改善するだけでなく、効率的な生産や作業の安全性を高めるためにも欠かせません。
優れたハンドブックは、そこで大きな役割を果たします。全員が同じ情報源を参照することで、業務の品質を均一に保つことができるわけです。
2)教育・研修ツール
新入社員の研修や、現役社員の継続教育において、基本的な知識やスキルを体系的に学ぶためのツールとしてもハンドブックは不可欠なものとなります。
日頃の業務で生じた些細な疑問を解決する入口として、社内サイトを参照するよりも素早くアクセスできるハンドブックづくりを目指しましょう。
3)リファレンス機能
日常業務における判断基準や、緊急時の対応手順など、重要な情報を環境に左右されず確認できるリファレンスとして、ハンドブックは欠かせません。
航空機などの緊急時マニュアルがなぜ今も完全にデジタル化されないのか、その理由を考えると印刷物の優位性が見えてくるのではないでしょうか。
ハンドブックの活用事例
ここからはハンドブックの具体的な活用事例をご紹介していきます。皆さんの業務環境にも当てはまるものがあるか、ぜひご覧ください。
1)社員手帳型
企業が掲げる理念や行動規範、就業規則や福利厚生制度など、社員が知っておくべき基本情報をまとめたハンドブックです。
新入社員にとっては会社を理解するための入門書として機能し、現役社員にとっては必要に応じて各種制度を確認できる便利なソースとなります。
主に企業理念やビジョン、組織図や部門・部署の説明、就業規則の要約や各種手続き方法、福利厚生制度や緊急時の連絡先リストなどを掲載していきます。
2)業務マニュアル型
特定の業務や職種に関する手順、基準、注意事項などをまとめたハンドブックです。
例えば、接客業であれば接客マニュアル、製造業であれば現場での作業手順書などが該当します。
標準的な業務フローや作業手順のほかに、チェックリストやトラブル対応のTIPS、用語集、簡単なQ&Aなどが掲載されることが多いです。
3)安全衛生に関する注意喚起型
主に工場や建設現場などで使用される、安全管理に関する重要事項をまとめたハンドブックです。
事故防止のための基本ルールや緊急時の対応手順などが記載されます。
基本的な安全ルールや危険予知活動の方法、保護具の使用方法や緊急時の対応手順、事故報告の方法や応急処置の手順などがまとめられています。
4)商品・サービス説明型
営業担当や販売員が使用する、商品やサービスの情報をまとめたハンドブックです。
商談や接客の場面で、即座に必要な情報を確認するために用いられます。
商品やサービスの特徴、仕様やスペック、価格、よくある質問と回答、導入事例などを掲載します。
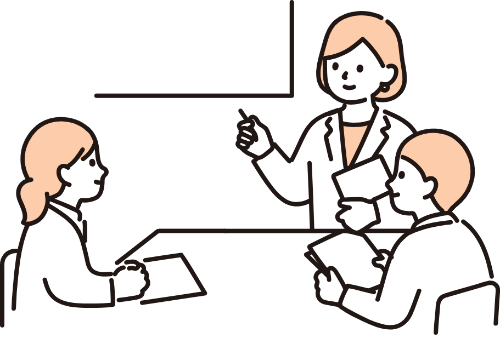
ハンドブックを制作する場合、まずは目的を明確にすることが最重要となります。
誰のために作るのか、どのような場面で使用されるのか、どのような効果を期待するのかを制作の初期段階で明確にしておきましょう。
次に、適切なサイズとボリュームを検討します。
「ハンドブック」と呼ぶ以上、携帯できなければ意味がありませんので、用途に応じた適切なサイズを選択することが求められます。
必要十分な情報量を見極め、携帯性と可読性のバランスを考慮します。
情報が過剰に詳細になってページ数が増加したり文字が小さくなったり、逆に情報を間引きすぎて知りたいことにたどり着けないものにならないように注意しましょう。
また、作業手順や優先度に応じた目次構成、過不足のない情報の配置、検索性の高いインデックス設計を心がけてください。
そして、コンテンツ作成時には、とにかく分かりやすさを追求しましょう。
平易な言葉を使い、箇条書きや図表を効果的に活用して、本当に重要なポイントだけを強調していきましょう。
また、言うまでもなく、内容の事実確認をして正確性を確保しなければいけません。
必ず関連部署によるレビュー(校正・校閲)を受けましょう。
ハンドブックの製本方法としておすすめなものが、「無線綴じ(くるみ綴じ)」と「中綴じ」です。
無線綴じ(くるみ綴じ)は、本の背を糊で固めて綴じる製本方法で、耐久性の高さが特徴です。
使用機会が多く、丈夫さが求められるハンドブックで多く用いられています。
これに対して中綴じは、二つ折にした紙の折目の部分をホチキスで留める製本方法です。
軽量で丸めることもできるので携帯性は高いのですが、無線綴じ(くるみ綴じ)と比較すると耐久性は劣るため、使用環境や頻度に応じてお選びください。
冊子印刷ドットコムでは電子ブックの制作も承っております。
アナログ・デジタル双方の特徴を活かし、相互に補完する存在として、ぜひご用命ください。
ハンドブックは決して一度作れば完結するというものではありません。
定期的な内容の見直しや更新、使用状況のモニタリングを行い、より効果的なツールとして育てていくことが大切になります。
私たち冊子印刷ドットコムは、創業以来55年、「冊子の制作に強い印刷会社」として高く評価して頂いております。
年間で100万冊以上という経験と実績で、皆さまの組織に最適なハンドブックづくりをスタッフ一丸となってサポートさせていただきます!



















