校正・校閲の世界〜私たちの暮らしを支える「文字」のプロフェッショナル

私たちの生活は、かつてないほど文字情報で溢れています。
スマートフォンやパソコンの画面をはじめ、本や新聞、雑誌や商品パッケージ、説明書などにいたるまで、一日に目にする文字の量は膨大です。
これらの文字情報が、正確で読みやすい形で私たちの手元に届くのは、決して偶然ではありません。
多くの「縁の下の力持ち」たちが、細心の注意を払って文字情報の品質を管理しているのです。
その中でも特に重要な役割を果たしているのが、「校正」と「校閲」という仕事です。
一見似ているように見えるこの2つの仕事は、それぞれが異なる専門性を持ち、私たちの文字情報の質を支えています。
今回の記事では、普段はあまり目にすることのない校正・校閲の世界について、基礎から実践まで、詳しくご紹介していきます。 校正(こうせい)の仕事とは、文章の体裁や形式的な誤りをチェックし、修正する作業です。主に以下のような点に注目してチェックが行われます。
1)文字に関する確認
誤字・脱字、漢字の正確さ・送り仮名の確認
同音異義語の確認
句読点の使い方の確認
仮名遣いの統一
2)体裁に関する確認
文字サイズや書体の統一
行間や文字間隔の調整
段落の配置
インデントの統一性や余白の調整
3)文章全体の構成に関する確認
図表やページ番号の確認
目次と本文の整合性
章立ての一貫性
例えば、「今日は晴れでしょ」という文章があった場合、「今日は晴れでしょう」と助詞を正しく修正したり、「私達」と「私たち」が混在している場合に表記を統一したりするのが校正の仕事です。
これに対し、校閲(こうえつ)は文章の内容の正確さをチェックする作業です。
1) 事実関係の確認
歴史的事実や統計データ、根拠となる科学的知見、固有名詞の表記、年代や日付の正確性
2)専門的観点からの確認
専門用語や業界固有な表現の確認、技術的な説明・法律用語・医学用語の適切性
3)倫理的・法的観点からの確認
著作権・商標権への配慮、個人情報の取り扱い、差別的表現の有無や名誉毀損の可能性
例えば、歴史書の中に「明治維新は1867年に起きた」という記述があった場合、実際は1868年が正しいため、この事実誤認を指摘するのが校閲者の役割です。
このように、両者の最大の違いは、校正が「形式面」をチェックし、校閲が「内容面」のチェックを担当するということです。
校正は目に見える誤りの修正、表記の統一、体裁の整備を主な仕事とします。
これに対して校閲は内容の正確性確認、文章の整合性チェック、表現の妥当性判断を担当するわけです。
私たちが日常的に目にする様々な文字情報の1つ1つには、以下のような校正・校閲という重要な工程が組み込まれています。
一般の出版物においては、内容の正確性を保証し、同時に読者への配慮をしつつ読みやすさを確保します。
それによって著者の意図を正確に伝達することができ、その書籍のブランド価値を維持することができます。
新聞や雑誌での主な役割が速報性と正確性の両立です。
そのためには事実確認を徹底して確認し、公平性を確保します。
そういった社会的影響への配慮なしでは 読者からの信頼獲得は難しくなります。
学術出版の際には、研究成果の正確な伝達ができなければ、せっかくの成果が台無しになってしまいます。
このため専門用語の適切な使用、引用の正確性確保、論理的整合性の確認を行い、国際的な通用性を確保します。
ビジネスにおける校正・校閲の重要性もますます高まっています。
ブランド価値の保護や専門性の表現、そして信頼性を確保することで顧客との関係が構築でき、競争力を維持できるわけです。
SNSの普及を背景に、軽微な誤植がまたたく間に世界に広がっていくなどというリスク管理の観点も必要です。
法的リスクや風評被害を回避し、クレーム対応を削減することでコストにも良い影響が生まれます。
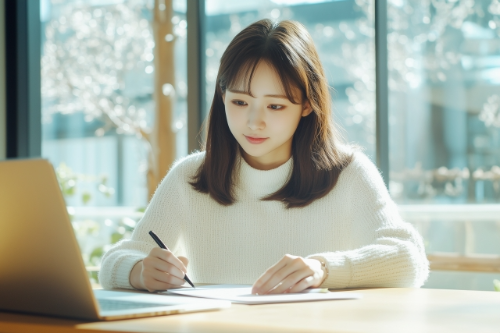
では、プロの校正・校閲担当者になるにはどうすればいいのでしょうか?
まず何よりも日本語の高度な知識、正確な文章読解力が必要なことは言うまでもありません。
その他、細部への強い注意力や幅広い一般教養、論理的思考力、さらには専門分野における特定分野の専門知識や外国語能力も必要となるでしょう。
そして大学での国語・文学系学部での学習を経て、出版会社でのアシスタント経験や実務経験を積み重ねていきます。
その後、フリーランスの在宅ワーカーとして活躍していくことも可能です。
しかし、校正・校閲はこのような経験をしてきた人だけができるものというわけではありません。
いわゆるプロでなくても実践できる、校正・校閲のコツを学んでいきましょう。
まずは基本的なチェックを行います。その基本中の基本が誤字・脱字のチェックです。
「文章を声に出して読む」など効果的な方法として知られたものもありますが、いずれにしてもまず「1文字ずつ確認する」「特に数字は慎重にチェックする」といった基本中の基本は忘れないようにしましょう。
次に体裁のチェックとして、詳細な文章チェック→形式面の確認→総合的な見直しと進んでいきます。
チェックの際は、できるだけ複数のスタッフが目を通すような態勢を整備しておきましょう。
また、実際の校正・校閲は、スペルチェッカーなどのデジタルツールを活用していくのもいいでしょう。
校正と校閲は、文字情報の質を支える重要な仕事です。
形式面と内容面、それぞれの専門性を持って文章をチェックすることで、正確で読みやすい情報を届けることができます。
デジタル化が進む現代においても、むしろその重要性は増しているといえるでしょう。
情報の信頼性が問われ、一度失った信用を取り戻すのが困難な今日、校正・校閲の果たす役割は、ますます大きくなっています。
プロフェッショナルな校正・校閲者を目指す方はもちろん、日常的に冊子づくりに携わる方々も、基本的な校正・校閲のスキルを身につけることで、より質の高い文章作成が可能になります。
冊子印刷ドットコムの大学論文ゼミ卒論印刷サービス「まるっとゼミ得」では、専門の校正スタッフによる内容確認も行っていますので、ぜひご用命ください。
私たち冊子印刷ドットコムは、長年の無線綴じ(くるみ綴じ)・中綴じ印刷での冊子づくりの経験をもとに、皆さまに正確で読みやすい印刷物をお届けしています。
苦労して校正・校閲を通して皆さまの印刷物を、ぜひ冊子印刷ドットコムにお任せください。
経験豊富なスタッフ一同お待ちしております!



















