製本をするポイントは?製本って本当にいるの?
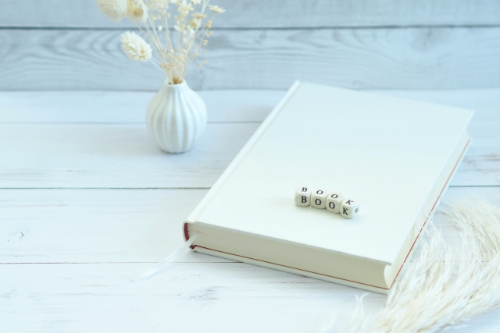
製本というのは必要なのか、それとも不要なのか疑問を抱かれる方も多いのではないでしょうか。
この製本というのは、小説を書いている人、同人誌を作っている人にはもちろん、実はビジネスにおいても、契約書を作る時に製本が必要になります。
ビジネスにおいて取引の場で交わされる契約よは、枚数が多くなればなるほどどうしても製本が必要不可欠になります。
どうして製本が必要になるのか、ですがバラバラの状態で保管をしていると書類の中抜け、紛失の原因になってしまいます。
それはトラブルの元になります。
契約書はただホチキスで留めるのも良いのですが、見た目があまりよくありませんので製本をしておくのがおすすめです。 ホチキス留めをした場合には、契約書の内容すべてのページに対して割り印が必要になるのですが、製本をすると表紙、背表紙への押印だけで問題ありません。
見た目もとてもきれいな仕上がりになる契約書ですので、取引相手に与える印象もとても翌なります。
製本の方法
製本をするためには必要最低限必要なものがあります。
製本したいと思っている契約書、はさみ、ホチキス、製本に使用するテープが必要になります。
まず、契約書をまとめてホチキスで留めます。
書類のはしから5ミリ前後のスペースをあけます。
そこをホチキスで2箇所留めます。
書類の端から5mmくらいスペースを空けて2箇所ホチキスで留めておくのがおすすめです。
契約書の厚みを測定しておきます。
枚数が少ないものであれば厚みを測る必要はありません。
次に製本テープを切っていきます。
製本テープには色々な種類があります。
中にはA4サイズにカットされているものもあるのですが、多く使用されるのはロールタイプの製本テープです。
カットをする時には契約書のサイズピッタリに合わせるのではなくある程度は余裕をもってカットしてみてください。
失敗しにくくするためにも、このカットする長さに余裕を持たせるというのはとても重要になります。
カットした製本テープを貼る位置を決めていきます。
契約書をテーブルの上において、貼る位置を決めていきます。
位置が決まったら、製本テープをはがしますが、はがすときに曲がってしまったり、斜めに貼り付けてしまうことがあります。
製本テープは裏面のはくり紙中央に剥がしやすいように切れ目が入っています。
他てにした時には左右に剥がせるようになっていますので、半分ずつ剥がすようにしてください。
半分だけ剥がしたら、剥がしていない半分のテープの上に定規などのまっすぐなものを置いて固定します。
容易が垂直になっていることをっ確認しながら貼り付けます。
貼り付けたら、製本テープの余っている部分を切り取ります。
次に契約書の裏面です。
はくり紙を剥がしたら折り目をつけて書類中央から端の方に張り付けていくときれいに貼り付けられます。
全ての用紙を貼り付けたら定規などで細かいシワをしっかりと伸ばして仕上げていきます。
製本テープを使ってきれいな仕上がりにするためにはテープのサイズに注意するというのが重要です。
契約書が分厚くテープの長さがギリギリ、ということもあります。
テープカットをする時にはサイズ感に注意してください。
上下に5センチ前後のゆとりがあるときれいに仕上がります。

また、ホチキスは製本をする時に極めて重要な骨組みとなる部分です。
しっかりと固定できるようにしてください。
1か所留めだとどうしてもずれてしまいますので、書類の端から5mm程度の空白をあけて複数個留めるようにしてください。
書類が分厚ければ2箇所よりも3箇所留めるようにしてみてください。
そうするとより安定します。
契約書の枚数によって使用するホチキスの針の太さ、長さ、個数を変えてみてくださいね。
また、印刷する時には、綴じるということを前提にして印刷してみてください。
製本できたとしても書類を開いてみると綴じた部分に文字が重なってしまい、文章が読みづらいということもあります。
書類を綴じるということを想定して、しっかりと余白を設けて印刷してくださいね。
製本してしまうとテープをきれいに剥がすことができないので契約書の印刷の段階からやり直さなければならなくなってしまいます。
また、製本テープはロール状態になっていますので、貼り付けやすくなります。
定規や重量のある本などで押し付けるようにして矯正するのもおすすめです。
製本というのは思っているよりもとても簡単に実践できます。
契約書などもただホチキスで留めるだけよりも、製本テープを使用するなどするだけで見た目がとてもきれいになりますので、ぜひ試してみてください。
もちろんホチキスを使用した中綴じも良いですし、中綴じでは綴じられない場合には無線綴じなどでより強く固定するというのもおすすめですよ。
目的、強度、仕様によってそれぞれに適した製本方法がありますので、ぜひ最適な製本方法で製本にチャレンジしてみてくださいね。



















