冊子を楽しく手作りする時のポイントや注意点は?
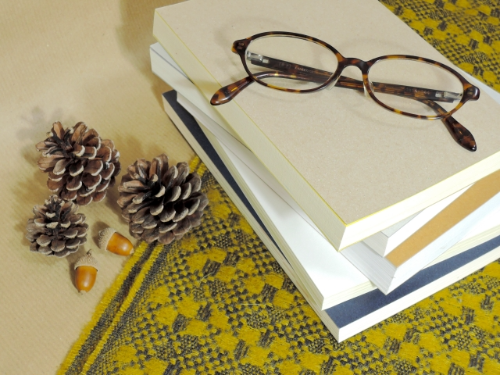
冊子というのは自宅でも実はとても手軽に作ることができます。
もちろん原稿だけを作って、あとは製本業者に依頼するというのもOKです。
冊子を作りたいと思っているけど、どうすれば作れるのかわからないという方にもわかりやすいように、簡単な冊子の作り方についてご紹介していきます。
冊子を手作りする時にまず決めておくべきこと
冊子を手作りする時にまず決めておくことがあります。
しっかりと手順を踏んでおかなければ冊子作りは失敗してしまいますが、手順さえしっかりと踏んでおけば問題ありません。
冊子作りをはじめる前の段階から注意しておくべきポイントについてもご紹介していきます。
まず、製本方法を決定します。
手作りをする時には、まずできるだけ簡単に、そしてコストをおさえて製本をするということです。
低コストで作れる製本方法としては並製本があります。
並製本は、無線綴じや中綴じが分類されます。
手作りする際に、押さえておきたい要素の一つが「なるべく簡単に低コストで作る」という点です。比較的低コストで作れる製本方法には、並製本(簡易製本)と呼ばれる「無線綴じ」と「中綴じ」があります。
1.無線綴じ
無線綴じは背になっている部分に専用の接着剤をつけて閉じています。
よく用いられる一般的な製本方法になります。
本文にする用紙を重ねたものを表紙用紙でくるんで接着するのでくるみ製本とも呼ばれます。
ページ数の多い冊子に対しても用いられる製本方法になります。
背表紙ができるので、書棚にも立てやすく並べやすいので見た目もとてもきれいに整理整頓できますし、長期的に保管しやすい製本方法になります。
書店などで売られている本の大半はこの無線綴じによって製本されています。
2.中綴じ
中綴じは表紙と用紙を二つに折って中央部分をホッチキスによって綴じる製本方法になります。
背表紙ができないのですが、ページ数が少ない冊子においても用いることができます。
パンフレットやページ数の少ない本に適しています。
無線綴じよりも本をしっかりと広げることができるので見開き全体で表現したいような場合に適しています。
製本方法が決まったら、次はサイズを決めていきます。
手作りであればA4、B5あたりが扱いやすいです。
冊子によって適しているサイズが異なりますので、完成をした冊子をしっかりとイメージしながら決めるようにしましょう。
パンフレットや企画書のようにサイズが大きい方が読みやすいものであればA7をおすすめします。
同人誌などであればA4がちょうどよいサイズだと思います。
文庫本のようなサイズの本を作る場合には、B6サイズをおすすめします。
手作りする場合には仕上がりのサイズよりも2倍大きな印刷用紙が必要になります。
家庭用プリンターなどで印刷する場合には、サイズに注意してください。
右開き?左開き?
冊子を右開きにするのか、それとも左開きにするのかを決めていきます。
冊子の種類によって開き方は違いがあります。
文字がメインになる場合には右開きとなります。
カタログのように画像などがメインになる場合には左開きで本文は横向きになるのが一般的です。
カタログやパンフレットなどのように、画像やイラストが中心の構成の場合は「左開き」を選びます。左開きの場合、本文は基本的に横組みになります。これは英語版の冊子をイメージするとわかりやすいです。
原稿の構成が完成したら、構成に合うようにページ数を決めていきます。
目次を決めて、掲載する画像、投稿などをしっかりと考慮したうえでページ数を決めていきます。
そこに表紙をいれた全体のページ数を決めていきましょう。
面づけですが、すべてのページが16ページだとすると、用紙を奴折りにして重ねていいます。
背をテープで留めてページ数を書きこみ、いちどページをばらして原稿を作ります。
中綴じの面づけは、用紙を四つ折りにして中央部分で重ねて半分に折ります。
順番にページ数をかき込み、重ねた紙をバラバラにして順番通りの原稿を作ります。
原稿はwordやExcelなどのソフトを使って作るのが一般的です。
原稿のデータが完成したら、デザインの崩れている部分はないか、文字化けしている部分がないようにPDFファイルにして書き出しておくようにしてください。
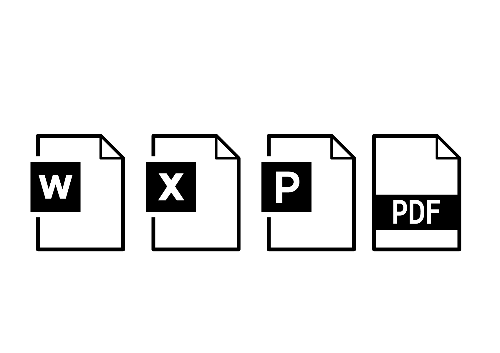
注意すべきポイント
本文のデザインをするときに注意すべきポイントは、無線綴じは背の部分をのり付けしているので中央部分にできるノドはすべて開くことができません。
そのため、ノド部分に文字、写真などが隠れないように注意しなければなりません。
ノド部分のデザインをしっかりと考慮したうえで作成しないと、重要な部分がノドで隠れてしまいます。
もじも見開き一面で情報を伝えたいと思うのであれば、その場合には無線綴じではなく中綴じを選ぶようにすると希望通りのデザインにすることができますよ。
無線綴じも中綴じも、自宅で製本できるのですが中綴じはとくに手軽に作れます。
ただ、自分で製本をするとなると失敗するリスクも高くなってしまいますので、大切な記念につくる冊子や、多くの部数が必要な冊子の場合には無理をせずに専門業者に依頼をするというのもおすすめですよ。



















