自分だけのオリジナル冊子を作る方法は?製本方法は?

自分のオリジナルの冊子をつくれたら良いな…
そのような方も多いと思います。
冊子を手作りで配布したり、自分で作った冊子を楽しむというのも流行ってます。
というのも、プロの作家さん、デザイナーだけではなくパソコンなどがあれば手軽に製本できるようになっているからです。
冊子を作るのは難しい、と思われている方も多いようですが、実はそんなことはありません。
冊子作りにおけるポイントについてご紹介します。
製本方法は?
まず冊子を作る時には製本方法を決めていきます。
手作りですので、できるだけ簡単に作りたいと思いますよね。
その場合、コストをおさえてなおかつシンプルな製本方法を選択すべきです。
コストを抑えて簡易的な製本方法を選択するとなると、やはり中綴じ、平綴じ、無線綴じなどがおすすめです。
無線綴じというのは背の部分に専用の接着剤を使用して綴る製本方法です。
本文の用紙に重ねたものを表紙でくるんでいきます。
ページ数の多い冊子に対しても使用できる製本方法になります。
背表紙ができる冊子なので、本棚などにも立てることができ、並べやすいというメリットがあります。
また、強度も高いので長期保存するうえでもおすすめです。
書店などに並んでいる書籍、文庫本などは大半がこの無線綴じです。
中綴じは、本の表紙、本文用紙とを二つ折りにしたものを重ねていき、中央部分をホッチキスなどで綴る方法になります。
パンフレットやページ数の少ない冊子におすすめです。
中綴じは無線綴じに比べると本を根本部分までしっかりと開くことができます。
見開き全体を使ったデザインなどにも対応しやすいのが魅力です。
二つ折りにした紙を重ねて綴るので、冊子全体のページ数は4の倍数となります。
糸かがり綴じは、糸を使った綴じ方で昔から用いられている製本方法です。
近年では中綴じ、無線綴じなどが増えていますが、糸かがり綴じは昔ながらの綴じ方で冊子そのものに趣もあり人気です。
糸かがり綴じは、ページ数の多い上製本にも用いることができ、製本強度が非常に高くページを大きく開いてもページが落ちるようなこともありません。
何度も読み返すような冊子や、ページを見開きいっぱいに開くような場合にはあまり適していません。
製本工程が多く、製本にかかる日数やコストもかかるのですが人気があります。
平綴じは、背表紙の内側を、針金で綴じていく強度の高い製本方法です。
ページの抜け落ちなどのリスクも低く、様々な髪質、ページ数にも対応してくれます。
サイズを決める
手作りで製本する場合には、サイズはA4、B5、A5、B6、あたりがおすすめです。
作りたい冊子がどのようなものなのかによって仕上がりのサイズも異なりますので、完成した冊子をしっかりと想像しながら決めていきましょう。
パンフレットなどのサイズが大きなものであればA4サイズ、同人誌などであればB5サイズ、小さなハンドブックなどであればA5サイズ、といったようにどのようなものを製本したいと思っているのかによってサイズは異なります。
手作りする場合には、印刷の用紙は仕上がりサイズよりも2倍ほどの大きさになるのが理想的です。
サイズと同時に、冊子の開き方も決めていきます。
冊子の開きは右開きなのか、左開きなのかを決定していきます。
開き方向次第で、原稿作りも大きく変わってきますので、冊子の種類や構成などを決める時に一緒に決めておくと安心です。
文字がメインになる冊子の場合には右開きが一般的で、その場合には縦組になります。
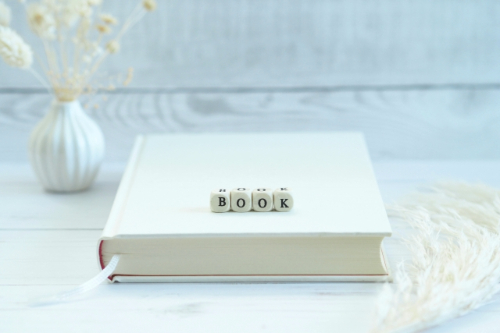
手作りの流れ
原稿の構成ができあがったら、構成にしっかりと合うようにページ数を決定していきます。
冊子のページ数を決めて、画像や原稿を考えたうえでページ数を決めます。
本文の大体のページ数が把握できたら、表紙を含めた全体のページ数を細かく決めます。
ページ数が決まったらページ順を確認していきます。
A4のコピー用紙を準備してページの配置を入念に確認します。
実際のサイズでなくても良いので、ページ順や配置を確認できるようにしておくと安心です。
ページ順に沿って原稿を揃えます。
原稿はワードやエク説などを使用して作成します。
文字化けなどのリスクもあるので、印刷会社に入稿するのが安心ですが、自分で行うのであれば丁寧に、入念に確認をしてみてください。
無線綴じの場合には、本文を表紙でくるむようにして製本しますので、表紙、本文とでデザインは変わります。
無線綴じは、背部分を糊付けするので中央部分のノドは開ききることができません。
見開きのデザインを使用したいという場合にはおすすめできません。
中綴じの場合には、見開きページを重ねて製本しますので、ページの順番がわかりにくくなってしまいます。
小口部分の文字などは切れることがあるので用紙の内側に文字などを入れておくようにすると安心です。
このように製本はしっかりとポイントを押さえておくことで、間違いなく、なおかつ低コストで手作りの冊子を作ることができるんですよ。



















