手作りで製本をしたいならどんな方法が良いの?
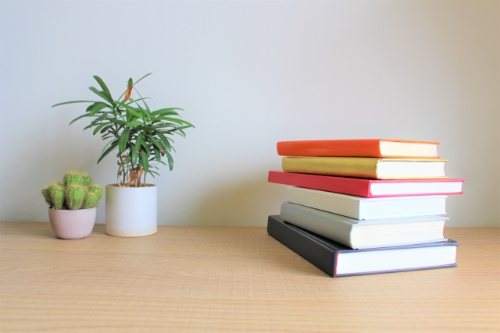
製本をしたいと思っているけどなにから始めれば良いのかわからない…
製本について調べてみても製本方法が色々ありすぎてわからない…
そのような方も多いと思いますので、まずは製本方法や種類についてご紹介していきます。
そもそも製本というのは、紙を綴じて合わせて本の形にするということです。
これが本を作るうえでの基本となる部分になります。
製本というのはとても奥の深いもので、製本方法も幅広いものです。 そしてそれぞれの製本方法にはメリットもありますしデメリットもあります。
まず製本には並製本、上製本があります。
小説、図鑑、説明書、漫画、パンフレットなどいろいろなものがあります。
そして並製本、上製本から中綴じ、無線綴じ、糸かがり綴じなどに分けられていきます。
製本方法によって印刷ページをどのように構成するのか、使用する製本機の種類も異なります。
並製本と上製本って?
並製本は、表紙の紙がとても柔らかくて、曲げるのが容易です。
ソフトカバーといわれるものです。
文庫本などによく使用されており、持ち運びもしやすいのが魅力の1つです。
上製本は表紙に厚紙を使用していて、皮などが使用されています。
ハードカバーと呼ばれるもので、図鑑などにも使用され、長期保管に向いています。
並製本のうちで、代表的なものが中綴じ、平綴じがあります。
これらは簡易製本と呼ばれており、非常にシンプルな製本方法になります。
中綴じ、平綴じというのは針金によって綴じられており、針金でどこを綴るのかによって中綴じ、平綴じに分けられます。
中綴じは背面からノド部分にかけて紙と平行に綴るものです。
ページを開いた時に、中央のページ部分に針金の先端が見えます。
中綴じは簡易製本と呼ばれるだけあって、作業工程が極めて簡単で、製本がスピーディです。
たくさんの正本数でも短期間で納品できますし、価格もかなり安く抑えられます。
また、ノドの部分を針金に寄ってとじているので、ページを開いた時にもしっかりと中央まで絵柄が見えます。
ただ、他の製本方法に比較すると強度があまり高くなく、長期的に保管をするような本には向いていません。
中綴じには背がないので本棚に並べた時に見つけにくいなど整理しにくいのが難点です。
無線綴じ、アジロ綴じがありますがこれらもとても一般的なものです。
専用の接着剤を使用します。
上製本で多く使用されるのが糸かがり綴じです。
印刷した用紙を糸をつかって綴じていきます。
糸の縫い方によって名称も変わりますが、耐久性があり長期的に保管するうえで適した製本方法になります。
昔から使われている製本方法で、和綴じなどもこの糸かがり綴じに分類されます。

印刷
冊子を印刷する時には、大きな紙を使って印刷しています。
1枚の大きな紙に複数枚分のページを印刷しています。
この印刷された紙のことを刷本と呼ぶのですが、よく使うプリンターなどのように1枚ずつ印刷るのではありません。
印刷する文書や絵柄などの並び方は、大きな紙から複数枚のページを印刷するというのを前提にして考えられます。
このことを面付けと呼びます。
そして印刷した用紙を折っていきます。
製本機に通し、折本を予定通りのページ順になるように折っていきます。
刷り本を1回、2回、3回と折り重ねていきます。
束を組み合わせていき、1冊の本にしていきます。
ページ物のデータを作る時には、このようなことからも4の倍数になるように意識しておくと、印刷の段階になって慌てずにすみます。
製本の仕方によっては、大きな刷本をまず切ってから製本機に通す場合もありますが、このような方法を大断ちと呼びます。
印刷と断裁が終わったら、ページの順番ごとに重ねられていき、針金を使って綴じます。
複数の刷り本があるのなら、刷本を重ねますが、これを丁合と呼び、この重ね方は製本の方法によって少しずつ違ってきます。
中綴じの場合であれば、製本機に乗せて、そこから内側のページから順番にページ数が多い方から重ねられていきます。
無線綴じなどの場合にはページや刷本ごとに重ねられていきます。
次に形をきれいに整えます。
とじた本というのは、それで完成ではありません。
塗り足した部分があったり、余分な部分があります。
綴じられている部分以外の不要な部分を切り取ることを化粧断ちと呼びます。
余分な部分を切り取って、きれいな本にします。
この化粧断ちをするのかしないのかで冊子の見た目は大きく変わってきます。
この化粧断ちをするところまでが製本の流れになります。
もちろん、製本方法によって多少の違いはありますが、基本的にはこの流れです
これから製本をしたいと思われているのであれば、基本的な流れについてしっかりと把握したうえで計画を立ててみてください。
そうすると、実際に製本をする時に工程の途中で失敗してしまったり、やり直さなければならなかったりというトラブルを回避できます。
製本は決して難しいことではありませんが、製本方法が持つ特徴、メリットデメリットや製本の流れを把握しておくのはとても重要ですよ。



















