ビジネス書や実用書を作るポイントは?無線綴じがおすすめ?
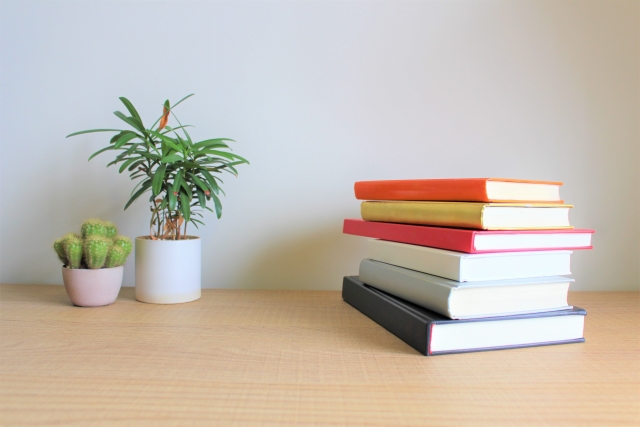
ビジネス書や実用書を作ってみたい!
という方もいると思います。
そもそも、ビジネス書、実用書というのはどのようなもなのかをご存知でしょうか。
基本的に、ビジネス全般におけるマニュアル、指南書のようなものをビジネス書と呼びます。
そしてビジネスという縛りではなく日常生活において役立つ技術や情報といったものをまとめたものが実用書と呼ぶのが一般的です。 書店に行ってみるとビジネス書コーナーなどもありますし、とても人気があります。
そのようなコーナーに並べられている単行本をビジネス書や実用書と呼びます。
このような販売されているビジネス書は、200ページ以上のページ数で構成されているものが多く、それは文字数にすると8万文字ほどのものが多いです。
イラストなどが多く使用されているものもあるのですが、8万文字から10万文字ないものの場合にはビジネス書にしてはボリュームが少なすぎるかもしれません。
ではこのビジネス書や実用書というのはどのような流れで作られるのでしょうか。
ビジネス書作成の手順は?
ビジネス書を作る時の流れですが、次のようになります。
まず企画の立案をして、章構成の作成をします。
項への落とし込み作業をして実際に執筆開始です。
ビジネス書はもちろん実用書もですが、書籍を作成する時にはいきなり文章を書くのではなく、しっかりと順を追って作り込んでいくというのが重要になります。
手順をしっかりと踏んでさえいれば、ビジネス書を作成するというのは難しいものではありません。
まずは企画を考えていきます。
そのビジネス書、実用書の概要やタイトル、構成、読者層の考察などといったものが記載されます。
その本を作る人の経歴などから読者にどのような情報を伝えられるのか、なにを伝えたいのかといったことを明確にして、同じようなビジネス書と比較をしてどんな違いがあるのかも意識しなければなりません。
次に章の構成をします。
大体ビジネス書の構成というのは同じです。
問題提起から始まり、問題の背景や解決策、そして最後をしめくくるまとめです。
ビジネス書はできるだけ専門性が高い内容にすべきですので、対象となる読者がビジネスマンであるということを基本に考えて構成を組み立てていった方が良いです。
章構成がある程度できたら、その章の中でどのような内容を書くのかをしっかりとピックアップして、調整をしながら最終的になにが必要なのかを決定していきます。
項目が上手く思い浮かばない場合には、思いつくことをどんどん書き出していって、それを後から絞り込むようにすると効率よく項目を決定していくことができます。
章と項目が明確になったら、いよいよ執筆開始です。
1章あたり2項目が目安です。
1項目2,000文字程度を目標にして記載していってみてください。
執筆が終了したら、推敲していきます。
誤字がないか、脱字がないか、全体的に読みやすい流れになっているのかどうかも確認していきましょう。
できるだけ複数回、推敲するのがポイントです。
何度も推敲を重ねることによって文章はどんどん読みやすくなっていきますよ。
執筆したら印刷をして、製本していきます。
製本方法ですが、無線綴じをおすすめします。

無線綴じって?
無線綴じというのは本文となる紙を表紙でくるんでいき、背表紙の部分に専用の接着剤を使用して綴じます。
本文の背になる部分を糊で固めて表紙を固定しますので、糸や針を一切使用しません。
そのような点から無線綴じと呼ばれています。
本文の枚数が多ければ多いほど背表紙も分厚くなるので、タイトルなどを文字入れできます。
無線綴じはコストを押さえつつもしっかりと丈夫で、なおかつ高級感のある仕上がりになりますので冊子を長期的に保存しやすいのが特徴です。
ある程度のページ数にもしっかりと対応できますし、ページ数が多ければ多いほど背表紙のデザインも自由度が増します。
分厚い本をコストを押さえて印刷して、保管をしたい方に最適ですよ。
ただし、ページ数の少ない冊子には適さない製本方法です。
ページ数が少なければ背表紙も薄くなるのでデザインの自由度も少なくなっていきます。
本文が数百ページ以上になるような場合でも問題なく製本できますし、本文がしっかりと糊付けされているので長期的に保管できます。
ビジネス書などのようにページ数が多く、そして長期的に保管したくなるようなものであればやはりある程度の強度は必要不可欠です。
本棚で保管をするという場合にも、背表紙を見ればどこに本があるのかがすぐに分かりますので、整理しやすく見栄えもとても良くなります。
ビジネス書というのは一度読んだらそれで終わりというものではありません。
何度も何度も読み返している方も多いですので、ある程度の強度が必要で、なおかつ何度も読み返すので本棚に置いた時に見つけやすいデザインのものがおすすめです。
中綴じに比べると、無線綴じの方が手間はかかりますが、それでも強度や保管のしやすさなどを考えると無線綴じがおすすめですよ。



















